
家を建てるにあたり、資金面での強い味方となってくれるのは住宅ローンです。しかし、その選び方によっては、将来的な返済負担は大きく異なってきます。支払いが家計を圧迫することのないよう、どのような住宅ローン商品や金利タイプがあるのかを知ったうえで無理のない計画を立てるようにしましょう。
現在、住宅ローンのメインは民間融資の銀行ローン、証券化ローンのフラット35、公的融資である財形住宅融資の3つとなっています。
銀行ローンは、都市銀行をはじめ地方銀行やネットバンクなどで利用することが可能です。金利タイプを選ぶことができ、金融機関ごとに特徴的な保証や金利特典などが用意されています。不動産会社と提携している銀行のほか、日頃から付き合いのある銀行、組み合わせたい別のローン商品がある銀行など幅広い選択肢から借入先を選べるのが魅力です。
最長35年の長期固定金利が特徴のフラット35は、銀行や信用金庫といった金融機関をはじめ、保険会社、住宅メーカーなどの業者でも取り扱いがある証券商品です。保証料や繰上返済手数料が0円というメリットもあります。20年以下の返済でさらに低金利の融資が受けられるフラット20、省エネ住宅など質の高い住宅を取得する場合に利用可能なフラット35S、といったプランもあります。
財形貯蓄をしている人が利用できる公的融資が、財形住宅融資です。5年固定金利型で、5年ごとに適用金利の見直しがあります。利用するためには1年以上財形貯蓄を続けていること、貯蓄残高が50万円以上あることなどの条件を満たすことが必要です。財形貯蓄は、その制度を導入している企業の社員だけが利用できます。
住宅ローンの利用に欠かせない金利タイプごとの特徴も知っておきましょう。
| 金利タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |
| 変動 金利型 |
一定期間ごとに金利の見直しがある | ・借入後に市場金利が低下すると、返済負担が小さくなる | ・返済シミュレーションが難しい ・借入後に市場金利が上昇すると、返済負担が大きくなる ・借入後に市場金利が大幅に上昇すると、未払利息が発生する可能性がある |
|
固定金利 |
契約時点の金利が一定期間固定となり、その後の金利を固定と変動から選択できる | ・固定期間中の返済シミュレーションがしやすい ・変動型に変更した後に市場金利が低下すると、返済負担が小さくなる |
・変動型に変更した後に市場金利が上昇すると、返済負担が大きくなる |
| 全期間 固定金利型 |
借入時の金利が返済終了時まで固定される | ・借入時に全体の返済額を把握できるため、返済シミュレーションがしやすい ・市場金利が上昇しても返済負担は変わらない |
・市場金利が低下しても返済負担は変わらない ・変動金利に比べて金利が高くなる傾向 |
どの住宅ローンを選ぶか考える際には、金利と返済額を総合的に判断することが大切です。前述した金利タイプの特徴を把握し、自分にはどのタイプが合うかを考えてみましょう。
例えば、今後収入が増えたり、支出が減る見込みがあったりする場合は、市場金利上昇により返済額が増加した場合でも対応できる変動金利型がおすすめです。また、子どもの学費などしっかりと計画を立てたうえでやりくりしたい場合には、返済計画を立てやすい固定金利型が無難でしょう。つまり、自分の状況や環境によって、借入時の市場金利だけでなく将来的なライフプランを考慮することが重要な判断材料となります。
また、住宅ローンを組む際の諸費用の中には、保証料と呼ばれるものがあります。保証料は、債務者がローンの返済ができなくなってしまった場合に、保証会社が代理で銀行に弁済するための費用です。数十万円を求められることもある保証料ですが、保証料無料のローンも存在します。ただし、その分金利や手数料といった別の費用が高くなることもあるため、初期費用のみを見て決めないことが大切です。
住宅ローンは一般的に、物件価格の8~9割程度まで融資を受けることができるとされています。そのため、頭金は最低でも1~2割以上用意しておきたいところです。確かに、ローン商品の中には頭金ゼロをうたっているものもあります。しかし、頭金ゼロで融資を受けると総借入額が増えて、毎月の負担も大きくなるため注意が必要です。物件価格だけでなく、各種手続き料、引っ越し費用や当面の生活にかかる諸費用も含め、余裕をもった資金計画を立てることが大切です。
夫婦や親子など、同じ家に住む2人がそれぞれに住宅ローンを組むのがペアローンです。借り入れ条件を満たしたお互いが連帯保証人となり、どちらかが返済できなくなった場合にはもう片方が弁済する仕組みです。ローンを2つ組むことになるため借入額を増やすことができ、2人とも所得税を払っている場合には両方が住宅ローン控除の対象となるメリットがあります。
団体信用生命保険は、債務者が死亡または高度障害など万が一のことが起きた場合、保険会社から保険金により住宅ローンの残高を全額弁済する制度です。民間ローンでは加入を必須としているところも多くなっています。また、疾病保障付住宅ローンという、3大疾病(がん・脳卒中・心筋梗塞)をはじめとする慢性疾患への保障を含めた住宅ローンも増加傾向です。債務者が保障対象となっている病気になってしまった場合に、医師の診断をもとに住宅ローンの残高が0円になるローンを指します。
住宅ローンを組む際に必ず利用したいのが、住宅ローン減税制度です。個人が住宅ローンにより新規で自宅を取得または増改築した場合、各年の年末残高の1%×10年間が所得税から控除される仕組みです。(2021年12月31日までに居住することが条件)
住宅ローンを利用する際には、いくら借りられるかではなく、毎月いくら返す必要があるのかを基準に、計画を立てることが大切です。利用条件や諸費用など複雑な項目も多いため、担当者に相談しながらシミュレーションするといいでしょう。
>>【無料小冊子プレゼント】「本当にいい家」に住みたい人に知ってほしいこと
【オススメ記事】
・還付金が最大50万円!知って得する住宅ローン控除の基礎知識
・新築住宅を建てた後にかかる税金。10年間でいくらになる?
・長期優良住宅では定期点検が義務。アフターケアで長持ちする家に
・2019年の消費税率増で住宅ローン控除(住宅ローン減税)はどうなる?
・住宅ローンは自己資金なし、全額ローンでも借りられる。そのメリットとは
 Read More
Read More
くらし
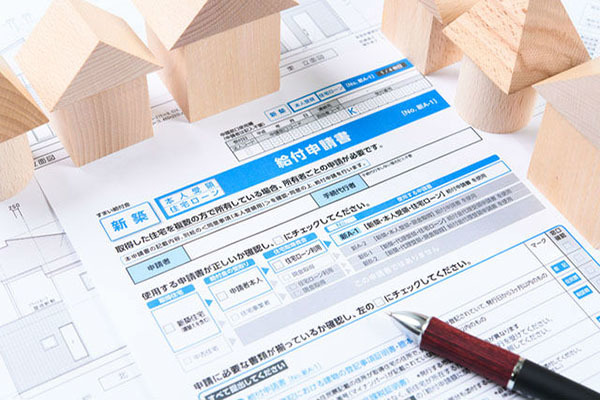 Read More
Read More
くらし
 Read More
Read More
くらし
 Read More
Read More
くらし
 Read More
Read More
くらし
 Read More
Read More
くらし
 Read More
Read More
くらし
 Read More
Read More
くらし